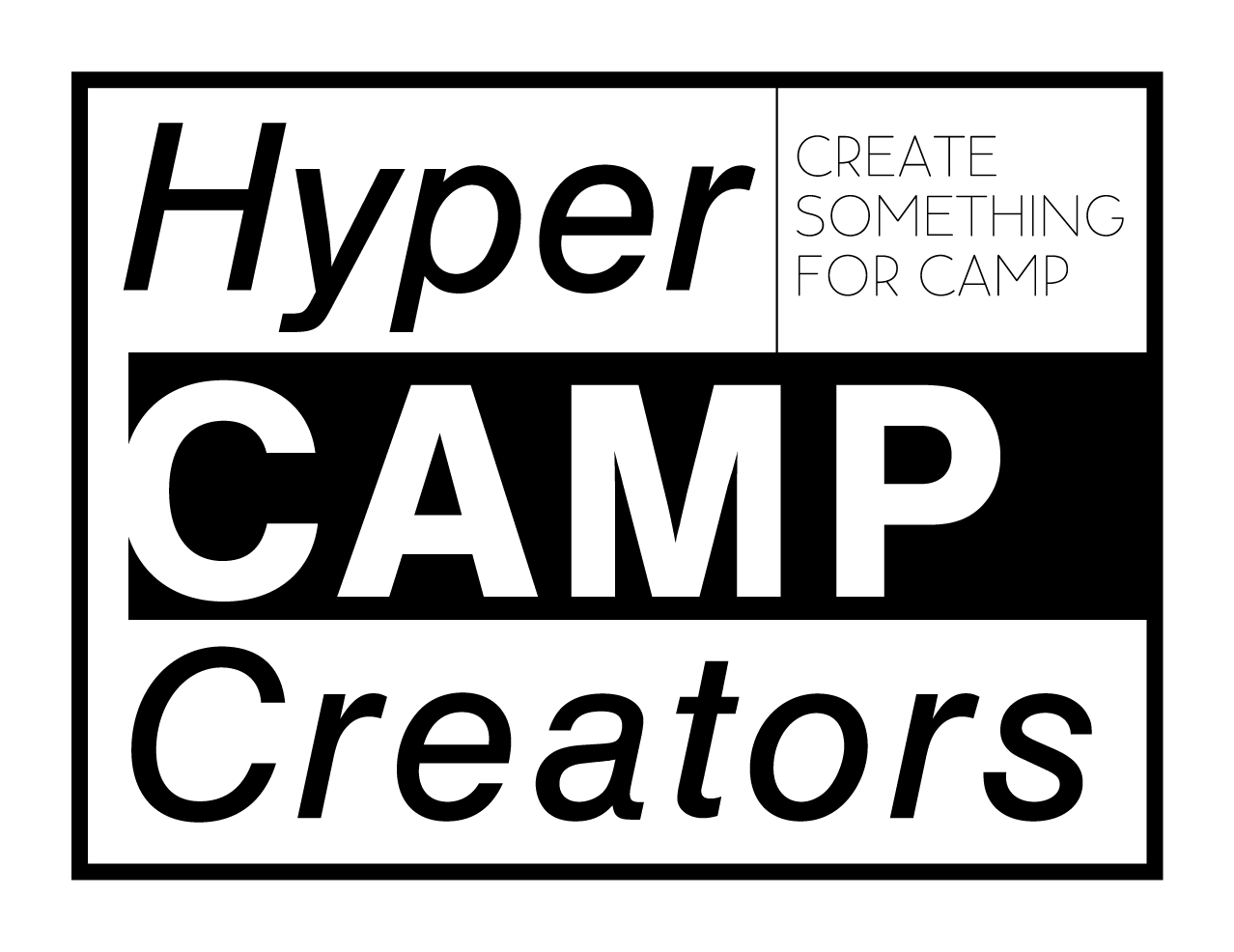どもども、ヤマケンです。
久しぶりの記事ですが、突然のパックラフトの話です。
昨年、初めてパックラフトというものを体験しまして、そこからバチバチにドハマリして、ここ数ヶ月は毎月1回は最低でも川下りをしています。

このパックラフトの面白さをよかったらみんなにも伝えたいなと思っておるわけでありまして、今回は「そもそもパックラフトってなんなん?」「どんなメーカーが出してるん?」的なお話をさささっと書いていこうと思います。
ただ、自分で経験している途中なので情報の精度が甘い場合もありますけれども、その辺りは事前にご了承ください。
シリーズ的に書いて、最終的にはパックラフトで川下りつつ、キャンプも楽しめるようなところまでお話するつもりです!
ではお付き合いのほどよろしくお願い致します。

その道のプロじゃなくて愛好家なので間違ってたらすまんな。
そもそもパックラフトってなんなの?

パックラフトは川下りや湖で楽しむためのアイテムです。
語弊を恐れずに超雑に説明しますけども、一人〜二人用の小型で超軽量な超強化ゴムボートのようなものです。
ラフティング(Rafting)ってあるじゃないですか。複数人数で大きいゴムボートに乗って、激流下っていく遊び。東京だと御岳エリア、埼玉の長瀞エリア、北関東だとみなかみエリアあたりが有名なところかなと思います。
ラフティングってそもそも英語だと「ボート」「いかだ」みたいな意味の言葉で、要は川下り用のボートそのものを表す名詞なのかな?知らんけど。

で、パックラフト(Pack-raft)ってのは、そのラフト(Rafting)をパック(Pack)出来るよーってなもんで、
バックパックにパッキング、つまりしまえるボートですよーって感じです。
パックラフトは電車で川下りに行って電車で帰ってこられる

そういうわけで、パックラフトは持ち運び簡単な超軽量な小型ゴムボート的なもので、その遊びを指すわけであります。
では、その軽量さと持ち運びしやすさにどんなメリットがあるかと申しますと、
電車で移動して、川下って、電車で帰ってこられる
というもの。
カヤックやカヌーで川下りをしようとすると、どうしても車が必要になります。
それにカヤックなどを運ぶためには車の上にキャリアの取付が必要になります。毎回車の上に載せて、落ちないように固定して、移動して、固定外して、下ろしてという作業。
さらに言えば、下りきったあとは、そのカヤックどうするん?ってなります。
最低でも車2台で出て、下流に一台、上流に一台置いて対応するか、下らないで上流から車でバックアップしてくれる人が必要かと思います。

その分アタックする川を選ばないというか、ホワイトウォーターバシャバシャがエグいところまでアプローチ出来たり、むしろメリットもたくさんあるのです。
一方でパックラフトは、バックパックに収まるくらいのサイズ感と重量なので、電車が並走しているような川を選べば、
電車で上流まで移動して川下り開始、駅が近い良きところで上陸して、またバックパックにしまってそのまま電車で帰る
なんてことが出来ます。
なので、より機動力がある、身軽手軽に川下りに行ける素敵アイテムなのです。
パックラフトってどれくらいのサイズ感と重量感なの?
ここまででパックラフトが軽くて小さくなって持ち運びが簡単、っていうことは分かって頂いたと思います。
では、実際にどれくらいのサイズ感で、重量はどうなのか?ってのが気になるところですよね。
サイズ感・重量については、パックラフトを出しているメーカーごと、モデルごとに細かくは違います。

参考までにですが、僕が使っているフロンティアのパックラフト(ペトロマックスの正規代理店をやってるスター商事さんが取り扱っている)CW-220だとこんな感じ。
- 本体重量3kg
- シート・バックレストなど0.5kg
- 合計3.5kg
これにヘルメットやパドル、ライフジャケットが必要になるので、最小限の装備は5キロ程度になるんだけど、それでも驚異的な軽さじゃない?
これで川下れるのやばない?
サイズ感は写真で見せるとこんな感じです。

写真真ん中上の黒い奴が畳んだ状態のパックラフト。
ちょっと分かりにくいかもですけど、本体だけで言えば小脇に抱えられるくらいのサイズ感に収まります。
パックラフトの全長や幅によりけりですが、
- 収納時の直径:70cm~90cm
- 収納時の高さ:40~50cm
こんな程度のサイズに収まるので、40Lのザックとかに収まります。すごいなこれ。
ヘルメット・パドル・ライフジャケットを一緒にしたとしてもこんなサイズ感。パドルは4分割に出来るので、結構小さく収まります。
下の写真の黒バッグ(フロンティアのパックラフトはこの黒い袋も標準装備です。)に丸めたパックラフトにライフジャケットを着せるような形で入れて、その脇に分割したパドルを差し込むようにするときれいに入ります。

黒いバッグに一式入ってます。灰色のザックが24Lサイズになるので、それで大体想像して頂けると幸い。
一泊二日の最低限のキャンプ用の装備を足しても、上の写真で収まるっちゃ収まるので、ほんと身軽で遊べるわけであります。

写真右のさくぽんが体の前面に抱えているのがパックラフトの基本装備です。
ぶっちゃけ、単純に荷物としては大きいなぁという感じはしますが、これで川下りできるちゃうってことを考えると、パックラフトの凄さが分かるのではないかなと。
パックラフトは安定してて川下りしやすい
あとはなんでしょうね。安定して川下りしやすいなぁという感じ。これはカヤックと比較してーとかではなく、単純にパックラフトで川下りをしてみての感覚の話です。

これまで、北海道の天塩川、栃木県から茨城県を流れる那珂川、茨城県の久慈川、熊本県の球磨川、東京都の多摩川(奥多摩)、埼玉県の荒川(長瀞)を下ってきました。
それぞれに瀬と呼ばれる白波が立って暴れている場所も大なり小なりあって、ちょっとずつ経験値をためております。

一番やばかったのは球磨川と増水したあとの多摩川で、めちゃくちゃ揉まれるような場所がありました。
で、それで思うのが、安定感あるんですよね。
船底がフラットなのと、エアーで水の上に浮いてる部分が多いからか、もろに横波にぶち当たることがなければスイーっと下れる気がします。
ホワイトウォーターじゃないような落ち着いたところを流れていくにはホント安定感あります。

一方で、ホワイトウォーター(瀬)に突入、パドル捌きをミスったりコース取りをミスって岩に接触などすると、まぁまぁ普通にチン(ひっくり返る)するので、その辺りは川下りの恐怖はもちろんあって、しっかりと練習なり、何かあったときの対処法を学んで実践しておくことは言わずもがな重要です。
とは言え、初心者が下るような川の瀬くらいはしっかりとパドリングの練習などをしておけば、安定して十分超えられます。
パックラフトは軽いからやばいと思ったら陸地を移動すればいいから川を選ばない
パックラフトのすごくいいところは、
- 「あ、この瀬は怖くて超えられない」と思ったら、持って陸地を移動して回避できる
- 治水用の堤防なども陸地を移動して回避するのが簡単
ということ。
軽量なパックラフトは、川下りの途中でもそれがメリットになります。
例えば、ものすごい白波が立っていて、自分の技術では超えられ無さそうな瀬に出会ったとき、事前に近くの河原に上陸します。
で、そのままパックラフトを担いで移動して、瀬が終わった先からまたスタートすることが出来ます。

また、川によっては洪水対策とかのために堤防が設置されている場所があります。そこを下って超えることは物理的に無理なので、こういうときもおとなしく上陸して、パックラフトを担いで超えちゃうことが出来ます。

これをポーテージという呼びますけれども、そんなわけで軽量だからこそ、そういう障害に当たったときに危険が無いように回避行動が取れる。
これがカヤックやカヌーだとなかなかこうは行かないので、これはものすごいメリットで、川を選ばず楽しめるわけです。

ちなみにですが、我々のホーム川の那珂川は堤防が無くてポーテージ必須な場所がないのですごく下りやすい。久慈川は堤防が何箇所かあって、何度かポーテージしないといけません。
パックラフトに初挑戦するならまずはスクール・ツアーに参加がおすすめです。

この記事を読んで頂いて、ご興味持たれた方にまずおすすめしたいのは「スクールやツアーにまずは参加すること」です!
これには2点理由があって、絶対に行ったほうが良いです。ちょっとお金はかかるけど、損しない。
- パックラフトの面白さを体感できて買う決心が固まる
- 安心・安全のための最低限の知識・技術を身につけられる
まず1点目ですが、ツアー・スクールは、その川を熟知したガイドさんたちが運営しています。なので、参加者の技量だったりレベルに合わせて、「ここだったら楽しめる」スポットに案内してくれます。
なので、初めてでもめちゃくちゃ楽しくパックラフトで川下りが出来るわけです。

実際、正直な話、最初は企業様とのお誘いでなんとなく行っただけで、行く前は買うつもりは一切なくて(買いやすい価格ではあるけど、安い買い物じゃない)。
でも結局一日コース満喫したら、その日の夕方にはどの挺を買うか真剣に悩んでいました笑
つぎに2点目ですが、これはもうわかりますよね。
パドルスポーツは単にパドルを振り回すわけではなくて、大事なスタンスだったり、漕ぎ方のテクニックがあります。
また、川を下るは一生流されるわけですが、だからこそ必要な知識が技術があります。
パックラフトがひっくり返ってチンしたときのセルフレスキューや心構えは自分の命に直結する問題なので、なおのこと絶対に受けておきたい。

例えば流れがなくなる場所と、そこへの入り方の技術は知っているか知っていないか、出来るか出来ないかでかなり違います。これをエディーキャッチっていうんですが、とにかく重要。
既にカヤックをガッツリやっているような方は大丈夫かもしれませんが、パックラフトとの感覚の違いは結構あるので、その辺りが不安な方もぜひ一度スクール・ツアーをやってみると良いかと思います。
ちなみに奥多摩の「みたけレースラフティングクラブ」さんには何回もお世話になっていて、ここ分かりやすくて、しかも楽しく体験できるのでおすすめです。ガイドの方も競技シーンにガッツリ出ている方なのでなおのこと安心


ちなみにスクール関係なく御嶽エリアにパックラフトしに行くと、ガイドのしょこたんが普通に川で練習している場面に出くわすので、「すげぇな」ってなります。
まとめ:機動力を活かしていろんな川にチャレンジできる、お手軽なソトアソビがパックラフト
そんなわけで、小型で軽量というのがパックラフトの特徴でした。
単純に移動手段に縛りがないということもそうですし、持ち運びのしんどさも比較的少ない。実際に川下りを始めたときも自分の技量に合わせてポーテージで回避することも出来るし、堤防超えもなんのその。
この特徴があるので、パックラフトは色んな川に挑戦しにいける、機動力のあるソトアソビアイテムなのであります。
もちろん、カヤックやカヌーと同様、川・水で遊ぶ危険性は常に隣り合わせです。
しっかりとした装備、事前準備、事前のパドル捌きの練習など、安全管理については十分に気をつけるべきですし、その恐れは絶対に持っておかないといけません。
でも、それを超えられるとめちゃくちゃおもしろいソトアソビが待っているのであります。まじで。
最初に話しました通り、キャンプとの組み合わせもバッチリなパックラフト。
次は、どんなメーカーのものがあって、どれを買うといいのかについて書きましょうか。現時点での私の知識を元にしたものなので最適解では無いかもしれませんが、興味が出た方はもう少々お待ちください!!